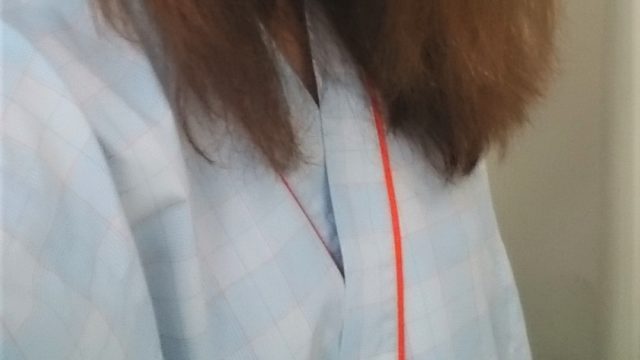子供にも、自分の意志で買い物をしたり、必要なものはお小遣いから支払ったり、お金の使い方を覚えていくことは大切ですね。
一般的に保護者の方はお小遣いをどのようにあげたり、いくらぐらい渡しているものなのでしょうか。
目次
子供にお小遣いは必要?
最近は、お小遣いに関する情報も色々とあって迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
お小遣いをあげて、お金の使い方や管理の仕方を学ぶことが必要だという考え方もあれば、何もしないでお金をもらえることは間違い、お小遣いは必要ないなど、両極端の考え方があったりします。
お小遣いは必要ないという考えの人もよくよく内容を見てみると、定額を渡すのではなく、お手伝いなど何か労働をした対価として渡す、というものであったり、必要なものを購入する時に渡すなど結果的には何らかの形でお小遣いをあげている人が多いようです。
お小遣いのあげ方

お小遣いのあげ方にはいくつか方法があります。
毎月決まった金額を渡す
お給料のように毎月定額をあげる方法です。買い物の計画が立てやすく、やりくりを身に着けるのに適しています。
必要な時に必要な金額を渡す
使い道を確認してからあげることができるので、何を買っているのか、無駄遣いをしていないかがわかりやすい方法です。
欲しいだけ買い与えてしまわないように、また、いつでも買ってもらえると思わせないようにする必要があります。
この方法は、金銭感覚が身につきにくいという考えもあります。
お手伝いの報酬として与える
お手伝をした内容によっていくらと決めてその金額を渡す方法です。
例えばお風呂掃除50円、洗濯物をたたむ30円、といった感じで、これを金額ではなくポイント制にしてもいいですね。
最初は大人が設定してあげてもいいですし、できることを自分で探すようになると、自立心や必要なことは何かを考えることにもつながります。
何より、自分が誰かの役に立つ喜びや、労働に対する対価を得られるやりがいも得られるのではないでしょうか。
これらを踏まえた上で、大人も子供も納得するあげ方を見つけていくといいですね。例えば、定額のお小遣い+お手伝い分という方法を採用しているご家庭もあります。
平均のお小遣いはいくら?
まず、お小遣いをもらっている割合として、小学生が約70%、中学生と高校生では約90%というデータがあります。
小学生
・小学生低学年(1~2年生)
平均額は約950円最も多い金額帯は500~700円で、次に多い金額帯は100~200円です。
・小学生中学年(3~4年生)
平均額は約900円最も多い金額帯は500~700円で、次に多い金額帯は1000~1500円です。
・小学生高学年(5~6年生)
平均額は約1100円最も多い金額帯は500~700円で、次に多い金額帯は1000~1500円です。
どの学年にも共通しているのが、一番多く回答された金額は500円で、高学年になるにつれて、1,000円~1,500円の金額帯が多くなっています。
中学生
平均額は約2500円最も多い金額帯は1000~2000円で、次に多い金額帯は2000~3000円です。
小学生と比較すると、倍の金額になっていることがわかります。
高校生
平均額は約5300円最も多い金額帯は5000~7000円で、次に多い金額帯は3000~4000円です。
中学生と比較するとさらに金額がアップしています。
お小遣いのポイント

お小遣いのあげ方を見ても、ご家庭での考え方の違いがあらわれていますし、
金額についても大体同じ価格帯が多いとしても、最も少ない金額と最も多い金額を比べると差はあります。ここで言えることとしては、「大体みんなこの金額だから」とか「あそこのおうちではこうだから」といった考えではなく、「うちの考えはこう」という意識が必要です。もちろん、親の一方的な押し付けではなく、お子さんと一緒に納得のいく方法や金額にするのが望ましいです。
そのために必要なのが、「わかりやすいルール」であることです。例えば毎月500円と決めたらそれを崩さない、とかこのお手伝いをしたら〇円、と決めることです。
世間や誰々さんがこうだから、という理由だと一貫性が保てない恐れがありますが、我が家ではこうであると決めておけばそれに流されることはありませんし、子供にもルールがわかりやすいので、混乱せずにすみます。
最初にやってみて、不都合が生じた場合には、親子で話し合って都度設定を見直していくのも良いでしょう。
あとは、あげたお小遣いの使い道については、つい気になってしまうところですが親が口出しせずに子供が考え、実際にお金を使って使い方や管理を学んでいくことが大切です。
最後に
お小遣いのあげ方は家庭によって違いがありますし、専門家のような人のお話などもあり、それも人によって考え方が違います。
こちらでは推奨されていても、あちらではダメな方法と言われている、、などという現象もあります。
子供によってお小遣いのあげ方の相性もあるので、親子の考えに合う方法を見つけましょう。